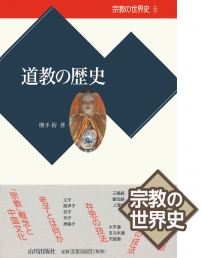
最近、道教の本を何冊か読んで、ネットでも調べてみて驚いた。日本の不可思議な宗教的な行事のほとんどが、道教から来ていたのだと思った。
本居宣長の「古事記伝」では、「神道は日本の固有の宗教」のように説明してあって、今も神道の側はそれを主張しているけれど、道教のことを学ぶと、神道が道教の影響を強く受けていることがわかる。道教を基にして作ったのだとしか思えないので、本居宣長の説明は間違いだろう。そう指摘している学者も多数いる。
不思議に思ったことは、日本ではそもそも「道教」について学ぶ機会がほとんどない。歴史の教科書や古典の授業の中でも、名前くらいしか出てこない。作為的に削っているようにさえ思う。
老子の「大道廃れて仁義あり(たいどうすたれてじんぎあり)」が出て来てたくらいしか、記憶にない。
しかし、七夕とか、七福神とか、古墳などに描かれる「四神」とか、様々なおふだとか、お守りとか、すべて道教からきたものであって、日本にはものすごい量・質ともに入ってきている。これ程の影響があるのに、どうして歴史や文化を学ぶ時に、外されているのかと、疑問に思う。
「神道」とは「かんながらのみち」というそうだが、要するに「かみの『道』」である。この『道』が、道教の中心的な教えだ。
柔道も剣道も茶道も華道も書道も、『道』がついている。柔術でも、剣術でも、茶の湯でも、生け花でも、書写でもいい。『道』がついているのは、『道』教思想によると思われる。
道教のことを詳しく学ぶと、神道は上書きされてしまう可能性がある。
因みに『辰砂』という道教の中で、永遠の命を得るための薬を作るための「硫化水銀」の結晶のことを「賢者の石」と呼ぶそうだ。ハリーポッターに出て来るこの石の元は道教だったのだと思った。ニコラス・フラメルは錬金術師だったようだが、「命の水」を得るために、賢者の石を作ったそうだが、中国には、すでに実在していたことになる。
秦の始皇帝初め、唐代の皇帝たちなど、多くの皇帝が中毒死している。これは、日本に入って来なくて良かったと思うけれど、古墳の中に遺体があれば、調べてみる必要があると思う。



コメント