
中学生の時だと思うけれど、第一次世界大戦の時の連合軍の写真として、上掲の写真を見た時にとてもショックを受けたことがある。右端が日本人で、あまりにも小さい。
そして、魏志倭人伝の「倭」の字の意味は「チビ」という意味だと、先生から説明を受けた。
そして、「わ」というのは、自分のことを「わ」と呼んでいたからだと聞いた。確か相手のことは「な」と呼んでいたとも聞いたように思う。その「わ」が「『わ』たし」となり、「な」が「『な』んじ」や「あ『な』た」になったとか。
どこまでが本当かの根拠は知らないが、そのように教えられた。
その「倭」を「和」と改め、「大和」としたのは、当時の日本人の意地だったのかも知れない。
でも、中学生の時は、とても腹立たしく思ったように覚える。
朝貢・冊封政策を取っていた中国(当時は中国ではないけれど…)から見れば、日本など取るに足らないものだったのだろう。
第二次世界大戦において、満州国を作り、中国を支配しようとしたのは、そうした積年の恨みだったのだろうか。
イスラエルの問題もそれよりも遥かに昔からの積年の恨みなのかも知れない。
今の日本は第二次世界大戦の被害国の恨みからは赦されてなく、イスラエルはイスラエルの戦後の支配統治に対するパレスチナ人の恨みに苦しめられている。
恨みからは良い物は生まれては来ないと思っても、恨みを消す方法は難しい。
いつか本当に赦される日は来るのだろうか。それとも、今のままではその恨みをかえって大きくしてしまわないのだろうか。平和への道は難しいと、つくづくと思う。


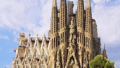

コメント