
【新改訳2017】マタイの福音書
5:7 あわれみ深い者は幸いです。その人たちはあわれみを受けるからです。
牧会心理学の授業の中で、「sympathy=同情」と「empathy=共感」という言葉を習った。日本語でもそうなんだろうけれど、「同情」という言葉にはあまりいいイメージがないのかも知れない。一時期「同情するなら金をくれ!」という言葉が流行ったことがあったように思うけれど、「同情されたくない」という気持ちがあるのだろう。同情されるというのは「みじめな」イメージが付き纏っているように思う。それで、「sympathy=同情」ではないく、「empathy=共感」を持って、カウンセリングをしましょう、というように習った気がする。
上記の御言葉の中の「あわれみを受ける」というところが、「幸い」なのだと、イエス様は教えられた。ここの問題は、「あわれまれたい」ですかということだと思う。誰かから憐れまれた時に、うれしいと思えるかということが、一番引っ掛かるところなのではないだろうか。
「あわれまれる」=「みじめだ」というように考えるとあわれみを受けることはできない。或いは「『かわいそうに』と言われると腹が立つ」というようだと、やはりあわれみを受けることはできないだろう。
だから、「あわれみ深い者」というのは、「あわれみ」を良いことだと思っている人のことだと思う。誰かをあわれむことも良いことなら、自分をあわれんでもらうことも良いことだと思っていて、あわれみを受け入れることのできる人のことだと思う。
誰かに「かわいそうに」と言われると、「自分はかわいそうな者なのだ」と理解して受け入れることができると、生きるのが少し楽になるのではないかと思う。
若い頃に、電車でお年寄りの人を見つけて、席を譲ろうとしたことがあった。相手の人は「いらん!」と、小声で鋭く一言、険しい顔で応えられた。その時の気まずさって…。本当に恥ずかしかった。自分は悪いことをしたのかと思った。すでに年寄だった母に、「お年寄りや不自由な人には席を譲ってあげてね。」と言われていたので、本当にびっくりした。それからは、何も言わずに席を立って、降りるフリをして、ドアの方へ行くことにした。
でも、前期高齢者となった今は、席を譲って頂けると素直に有り難い。
御言葉に戻るとしたら、「あわれみ」とは、「empathy=共感」なのだろう。「empathy=共感」を持つことのできる人は幸いだと思う。共感とは「共鳴(ともなり)」なのだろう。それは、思いを分かち合うことのできる能力だと思う。うれしい時に一緒にうれしいと思ってくれる。悲しい時に一緒に悲しいと思ってくれる。ツラい時に一緒にツラいと思ってくれる。そんな人が傍にいてくれるととても「幸い」だと思う。
子どもの頃聞いた歌に、「とんとんともだち」というのがあって、その歌詞に、「だれかが けがをした みんなが べそかいた」と歌っていた。こんな素朴でやさしくかわいらしい人間関係は、大人になって複雑怪奇な人間関係の大海原を泳がなければならない現代の私たちにこそ、必要なのではないかと思う。大人だけでなく、子どもの社会も今はこんなに単純ではないのかも知れない。
神様からのあわれみを受け取られますように、お祈りいたします。


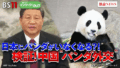

コメント